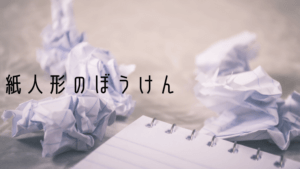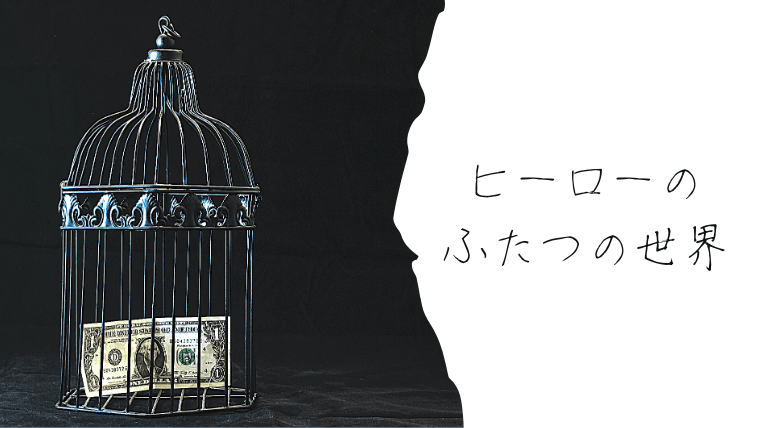今まで読んできたマーヒー作品と比べても不気味さ、暗い印象がかなり強いです。
また、他のマーヒー作品と同じく爽やかな読後感ではあるのですが、
手放しでは喜べない物悲しさも漂います。
対象読者は中学生向けとなっている本作ですが、だいぶ大人向け要素を含む本作。
訳者の方が初めて読んだときの感想として「恐怖を覚えました。気味の悪さにぞっとしました」と書かれている気持ちも、よくわかります…。
とはいえ、その後訳者の方がおっしゃるように、勿論それだけの話ではありません。
あらすじ
12歳のヒーローは、ここ三年ほどほとんど口をきかずに生活していて、緘黙症であると周囲からみなされてる少女。
ある日、近所の古びた屋敷の女主人ミス・クレデンスに出会い、屋敷の手入れのバイトを依頼されます。
割の良い屋敷のバイトを従順にこなすヒーローでしたが、ミス・クレデンスが庭に侵入してきた野良猫を撃ち殺すのを見て以来、何かがおかしいと思いはじめます。
感想
いわゆる場面緘黙症と呼ばれる症状がみられる主人公、ヒーローの物語。
ミス・クレデンスの不気味さが作中では特に際立っていますが、家族愛もその中でしっかりと描かれています。
ヒーローの母アニーは
"ふつうがすてき――子どもが世界とダンスするのを手助けする方法"
という本を書いて(↑いかにもありそうなタイトルじゃないですか?笑)一躍有名になった教育学者。
ヒーローと10歳以上年の離れた兄アソル&姉ギネブラは所謂ギフテッドと呼ばれる神童。
特にギネブラは、偶然メディアにインタビューされた際にその神童ぶりが注目され
"ふつうがすてき"の売り上げをぐんと上げることになった立役者でもありました。
そんなギネブラは「突然家を出ていった」と説明され序盤は不在。
中盤に家に帰って来るのですが、ギネブラ主人公でもお話が一冊書けてしまいそうなほど魅力的で、破天荒なキャラクター。
母アニーとギネブラの一見理想的に見えて、、、という関係には読んでいて胸が痛くなりました。
アニーはミステリーでも、ことばあそびでも、ジョークでも、ほら話でも、なんでも自分でこしらえてギネブラに話してやり、彼女となぞなぞ遊びをし、歌をうたってやった。
夜、ギネブラを外に連れ出すときには、ふたりは星を見るだけでなく、星と星の間の真っ暗な宇宙にも目をこらすことを忘れなかった。
「どこの親でもしていることをしただけです。」
アニーはきかれると、答えていた。
「わたくしたちは赤ん坊をいつも中心に置いたんです。ただそれだけ。それ以上でも以下でもありませんわ。」
けれどアニーが言うと、本人が自覚しているより、少しだけうぬぼれているように聞こえる。1
わたしは四歳のころ、ギネブラが何かおかしくなりはじめていると気づいたが、何がどうおかしいのか、よくわからなかった。
わたしがもう少し大きくなって家族の話に加われるようになったころには、ギネブラは何かにつけ腹を立てているように見えた。
「生まれてなんかこなきゃよかった。」
ギネブラはよくそう言って泣きわめいた。
「どうしてあたしを産んだのよ?なぜあたしには選択の自由がなかったの?」
でも、そんな風に怒っている時でも、ギネブラが生きることを愛しているのは誰の目にもあきらかだった。
思う存分生きたいのに、それができなくていらいらしているみたいだった。2
ギネブラだけでなく、このラッパー家の子どもたちはみんな自分の居場所を確立するためにもがいている印象です。
威圧的な印象のない、一見とても理解のある両親たちからの無意識の期待。
それに応えようとする子どもたちの葛藤がそれぞれの性格から見えてきます。
でもだからといって親が悪いわけでもなく…みんな一生懸命に自分がベストだと思うことをこなして生活しているんですよ。
愛情は確かに存在しつつも完璧ではない…ところどころいびつな、けれどリアルな家族の空気感が胸に迫ります。
そして、ヒーローが働く屋敷の女婦人、ミス・クレデンス。
彼女のお喋りのほとんどは偉大な学者である父のこと。
あたしは頭のいい子だった。
今もそうよ。あたしは知能指数上位二・五パーセントに入っているの。
それは間違いないわ、ちゃんと検査を受けたんだから。
それであたしはMENSAのメンバーになった。
あたしは輝かしい人生を歩こうと思えば歩けたかもしれないの。
でも父は……そりゃもちろんあたしのことを誇りには思っていたけど、頭のいい女性に対して世間は冷たいということを知っていたのね。
それであたしの袖をひっぱって、ここから出ていかないようにした。
あたしを守ろうとしてたんだと思う。
もっとも、あたしのためを思ってばかりじゃなく、
半ばは自分のためでもあったかもしれないけど。3
狂気的な喋り方から深い孤独と愛に飢えた少女のような物言いが垣間見えて、読んでいてとても切なかったです。
訳者さんがミス・クレデンスの一人称「I」を「わたし」ではなく「あたし」と訳しているのも、この精神面での未成熟な部分を反映させているのでしょう。すごい。
彼女のしたことは到底甘く見られるようなものではないのですが
亡くなった父の言葉に今も縛られて生きていて父親からの失望を受けたくない一心で行動しているところがなんとも悲しいです。
ミス・クレデンスは極端な例かもしれませんが、もうそこにはいない、過去の亡霊に縛られることは私たちの誰でも大いにあることなのではないでしょうか。
ギネブラが突然連れてきた男の子、サミーの存在がなければ
ヒーローもまたミス・クレデンスのような物語の中を夢見るように生き続ける人物になっていたかもしれません。
(さすがにミス・クレデンスほど歪みはしないでしょうが、二人は本質的な部分で似ている感じがします)
このサミーに関しては描写がとても少ないのですが
他の家族が自分のことで精一杯で、ヒーローと毎日接しながらもその異変に気が付かなかったのに対して
皮肉なことに、突然家に転がり込んできた闖入者である彼が一番きちんとヒーローのことを見ていてくれています。
どんな言葉をかけるよりも、ちゃんとその人のことを見てやることが一番大事。
作者はそう考えているのかもしれません。
また、主題ではないものの、この本は現代社会や教育についても考えさせられる要素が描写されています。
理想の教育を語り、大衆人気を獲得して裕福な稼ぎを得ているアニー。
けれど彼女自身の子どもたちは世間一般の常識からみると「問題を抱えている」子どもたち。
喋らなくなったヒーローは、シラサギ学園という少人数の所謂フリースクール的な立ち位置に通っていますが、自分がいつまでも喋らないことで教師を失望させていることを感じ取っています。
カウンセラーのひとりは、「被験者固有の症状に応じた治療法」を採用した。(わたしは被験者だったのだ。)
その人は初めのうち、「言語的ふるまいの積極的強化」と呼ばれる方法を試みてみた、と書いていた。
それは、もしわたしがたまたま何か声に出して言ったら、たとえそれがどんなにつまらないことでも、大騒ぎしてほめちぎるというやり方だ。
そういえば、公立の小学校に行っていたころ、わたしにだけ特別なカルテがあって、何かひとことでも言うと、丸をもらったり、金の星をもらったりしたことがある。4
喋らない主人公の物語ではそれに対して無理解な人物が描写されることが多い印象ですが、
この物語では、表面上では主人公に寄り添う姿勢を見せながらも、内心では戸惑いと落胆…ひいては操作しようとする大人の姿が描かれています。
両親も例外ではなく、母アーニーはヒーローが喋らないことを「罰」だと捉えています。
口では決してヒーローを責めませんが、その実内心では「話してほしい」という期待をこめて接している。言葉と本心がバラバラになっているのです。
育児論や教育論あふれる昨今を思うと、身につまされる描写でした。
作者がこの本で言いたかったことの一つは、知識や言葉ばかりが先行して、本当に大事な部分が置き去りになっていませんかということなのだと思います。
ラッパー家の住む高級住宅地では浮いたヒップホップスタイルの少年、サミーが、ヒーローを救う重要なきっかけを担っているのも、きっと狙ってやったのでしょう。
サミーは見た目こそただ商品を見ていただけで万引きを疑われるような風貌をしていますが、心と言葉が一致しています。
不可解なものを見ると名前をつけ、分類を行うことでその物事を理解したような気になるけれど、そうやって言い表すことのできるものはほんのわずかなのだというメッセージも感じました。
言葉を使う職業である作家さんだからこそ、言葉や知識が独り歩きしていく現代の在り方に危機感を感じていたのかもしれません。
SNSの普及でますますこの傾向が強まっていると思われる今。
この作品が20年以上前に書かれた作品だと思うとその鋭い洞察力にハッとさせられます。
マーヒーの別作品の感想はこちら↓ほっこりする読後感を体験したい時に是非。